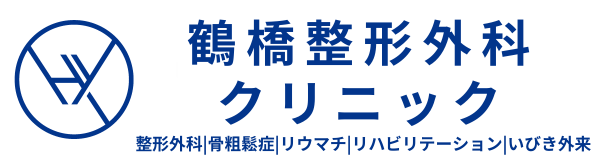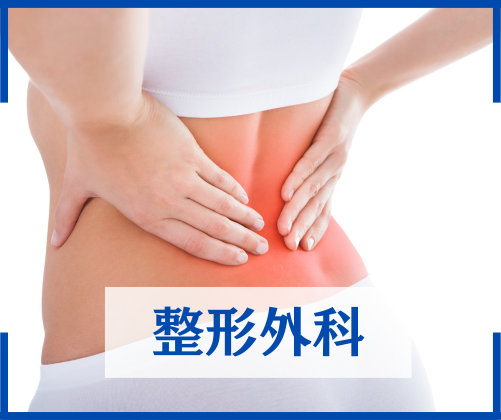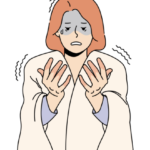ばね指の痛みや指の動きづらさを感じているのに放置すると、症状が重症化し、完全に指が動かなくなる「ロック現象」を引き起こす危険があります。本記事では、ばね指の初期症状から重症化のサイン、適切な受診先、手術を含む治療法まで徹底解説します。早期発見・早期治療がなぜ重要なのか、整形外科医の見解や患者さんの体験談を交えながら、日常生活で実践できる予防法や自己ケア方法もご紹介。「様子を見よう」と放置せず、適切なタイミングで医療機関を受診するための判断基準が分かります。
ばね指とは?基本的な症状と原因を理解しよう
ばね指(弾発指)は、正式には「ステノーシング・テノシノビティス」と呼ばれる一般的な手の疾患です。指を曲げ伸ばしする際に、引っかかりや痛みを感じる症状が特徴で、日常生活に支障をきたすことがあります。早期に適切な治療を受けることで症状の改善が期待できますが、放置すると重症化するリスクがあります。
ばね指の発症メカニズムとは
ばね指は、指を動かすための腱(けん)とその周りの腱鞘(けんしょう)という滑車のような構造との間に問題が生じることで発症します。健康な状態では、腱は腱鞘の中をスムーズに滑りますが、何らかの原因で腱や腱鞘に炎症が起こると、腱の動きが妨げられるようになります。
具体的には、指の腱が通る腱鞘に「滑膜」という組織があり、この部分が炎症を起こすと腫れて厚くなります。すると腱の通り道が狭くなり、腱の動きが制限されます。さらに腱自体も炎症により太くなることで、腱鞘との間に摩擦が生じ、指を曲げ伸ばしする際に引っかかりが発生します。
この状態が進行すると、腱の一部に結節(こぶ)ができることもあります。この結節が腱鞘の入口でひっかかることで、指を曲げたり伸ばしたりする際に「バネのように」急に動く現象が起こります。これがばね指と呼ばれる所以です。
ばね指の初期症状と特徴
ばね指の症状は、初期から重症まで段階的に進行することが多いです。早期発見・早期治療のためにも、初期症状をしっかり把握しておくことが重要です。
| 症状の段階 | 主な症状 | 特徴 |
|---|---|---|
| 初期症状 | 指の付け根の痛みや違和感 | 朝起きた時や長時間の使用後に痛みを感じる |
| 中期症状 | 引っかかり感と軽度のバネ現象 | 指を曲げ伸ばしする際に軽い引っかかりを感じる |
| 重症症状 | 明確なバネ現象と動作制限 | 指が固定されたり、他の手で助けないと動かせなくなる |
初期のばね指では、主に指の付け根(手のひら側)に痛みや圧痛を感じます。特に朝起きたときや長時間指を使った後に痛みが強くなることが特徴です。この段階では、まだ明確な「バネ現象」は見られないことが多いです。
また、指の付け根部分(手掌部)がわずかに腫れることもあります。この腫れは、触ると硬いしこりのように感じられることがあります。腱鞘の炎症によるものです。
初期症状に気づいて早めに対処することで、重症化を防げる可能性が高まります。朝の指のこわばりや、物を握った際の不快感など、軽微な症状でも継続する場合は注意が必要です。
日常生活でばね指を引き起こす主な原因
ばね指は様々な要因によって引き起こされます。日常生活における原因を理解することで、予防や再発防止に役立てることができます。
まず、過度な手指の使用が最も一般的な原因です。特に同じ動作を繰り返すことで腱に負担がかかり、炎症を引き起こします。例えば、以下のような活動がリスクを高めます:
- 長時間のパソコン作業やスマートフォンの操作
- 楽器(特にピアノやギター)の演奏
- 編み物や裁縫などの細かい手作業
- 園芸作業や大工仕事
- 料理や掃除などの家事
- 重いものを繰り返し持ち上げる作業
また、年齢も重要な要因です。40〜60歳の年齢層、特に女性に多く見られます。これは加齢に伴い腱の弾力性が低下することが関係していると考えられています。
さらに、以下の健康状態や疾患がばね指のリスクを高めることがわかっています:
- 糖尿病(腱の変性を促進する可能性がある)
- 関節リウマチ(関節の炎症が腱にも影響)
- 甲状腺機能障害
- 手首の腱鞘炎や手根管症候群の既往
- 手や指の怪我や手術の経験
職業的にも、手を多用する仕事(美容師、歯科医師、マッサージ師、建設作業員など)に従事している方はリスクが高まります。特に力を入れて物を握る動作や、指を曲げ伸ばしする繰り返しの動作が多い職業では注意が必要です。
その他、解剖学的な要因として、腱鞘の先天的な狭窄や、指の関節が通常より突出している場合なども、ばね指の発症リスクを高める可能性があります。
予防という観点からは、手指を酷使する作業の合間に適度な休憩を取ること、適切な姿勢や道具を使用すること、そして手や指のストレッチを定期的に行うことが重要です。また、症状の早期発見のために、手の異常な痛みや違和感に注意を払うことも大切です。
ばね指を放置するとどうなる?重症化のリスクと危険性
ばね指は初期段階では軽い違和感や痛みだけで済むことが多いため、「そのうち治るだろう」と放置されがちです。しかし、適切な処置をせずに放置することで症状は徐々に悪化し、日常生活に大きな支障をきたすようになります。この章では、ばね指を放置した場合の症状の進行と、重症化することで生じるリスクについて詳しく解説します。
軽症から重症へ:ばね指の進行ステージ
ばね指は進行性の疾患であり、放置すると徐々に症状が悪化していきます。一般的に以下のような段階を経て重症化していきます。
| ステージ | 症状の特徴 | 日常生活への影響 |
|---|---|---|
| 初期(ステージ1) | 指の付け根に軽い圧痛や違和感がある。朝に軽いこわばりを感じることもある。 | ほとんど支障なし。不快感を感じる程度。 |
| 中期(ステージ2) | 指を曲げ伸ばしする際に「カクッ」という引っかかり感が出現。軽い腫れや痛みを伴う。 | 細かい作業がやりにくくなる。痛みを感じることがある。 |
| 進行期(ステージ3) | 指が明らかに引っかかり、自分の力で引っかかりを解除できる。痛みが増す。 | 日常動作に支障が出始める。箸やペンの使用が困難になることも。 |
| 重症期(ステージ4) | 指が完全にロックし、他の手の助けがないと伸ばせない。強い痛みを伴う。 | 日常生活が著しく制限される。仕事や家事に大きな支障をきたす。 |
当院での診療経験から、多くの患者さんはステージ2〜3で来院されることが多いですが、中には「もう少し様子を見よう」と放置した結果、ステージ4まで進行してから来院される方もいらっしゃいます。進行したばね指は治療が難しくなるため、早期発見・早期治療が非常に重要です。
重症ばね指の辛い症状と生活への影響
ばね指が重症化すると、以下のような辛い症状が現れ、日常生活に大きな支障をきたします。
持続する強い痛み:初期のばね指では動かした時だけ痛みが生じますが、重症化すると安静時にも持続的な痛みを感じるようになります。この痛みは夜間に悪化することも多く、睡眠障害の原因になることもあります。
指の変形と可動域制限:長期間放置すると、腱鞘の炎症が慢性化し、指が曲がったまま固定されてしまうことがあります。これにより指の変形が生じ、可動域が著しく制限されます。
握力の低下:重症のばね指では、痛みや動きの制限により握力が大幅に低下します。これにより、ペットボトルのフタが開けられない、鍵が回せないなど、日常の簡単な動作さえ困難になります。
日常生活動作(ADL)の制限:以下のような基本的な動作が困難になります。
- ボタンの留め外し、衣服の着脱
- 箸やスプーンの使用
- スマートフォンやパソコンの操作
- 料理や掃除などの家事
- 書字や細かい作業
- ドアノブやレバーの操作
精神的ストレスとQOL低下:痛みや機能障害によって仕事や趣味活動が制限されることで、精神的ストレスや不安、抑うつ感が生じることもあります。生活の質(QOL)が著しく低下し、社会的な活動も制限されるようになります。
患者さんからは「痛くて眠れない日々が続き、精神的にも追い詰められていました」「仕事で文字が書けなくなり、休職せざるを得なくなりました」といった声も聞かれます。重症化する前の早期対応が、こうした生活への影響を最小限に抑える鍵となります。
放置による合併症や二次的な健康問題
ばね指を長期間放置することで、直接的な症状の悪化だけでなく、さまざまな合併症や二次的な健康問題を引き起こす可能性があります。
他の指への負担増加:痛みのある指をかばうため、他の指に過度の負担がかかり、別の指にも腱鞘炎やばね指が発症することがあります。当院の調査では、一本の指のばね指を放置した患者さんの約30%が、1年以内に他の指にもばね指を発症しています。
手首や前腕への影響:指の動きが制限されることで、手首や前腕に無理な力がかかり、手根管症候群などの別の障害を引き起こすリスクが高まります。特に、仕事でパソコン操作が多い方や、細かい手作業を行う職業の方は注意が必要です。
腱の永久的な変性:長期間の炎症により、腱組織が不可逆的に変性することがあります。この状態になると、保存療法での回復が難しくなり、治療期間の長期化や治療効果の低下を招きます。
関節の拘縮:指が長期間曲がったままの状態が続くと、関節が固まってしまう「拘縮」が起こることがあります。拘縮を起こすと、たとえばね指自体が治癒しても、指の可動域が完全には戻らないことがあります。
日常生活習慣の悪化:手指の機能低下により、調理が困難になって食生活が乱れたり、運動ができなくなって全身の健康状態が悪化したりすることもあります。実際に「料理ができなくなって外食や加工食品に頼るようになり、体重が増加した」という声も患者さんから聞かれます。
職業への影響:指の機能障害により、仕事のパフォーマンスが低下し、最悪の場合、職を失うリスクもあります。特に手先の細かい作業を必要とする職業(美容師、歯科医師、楽器演奏家、調理師など)に就いている方は、早期の対応が職業人生を左右することもあります。
ある患者さんは「最初は我慢できる痛みだったので放置していましたが、半年後には指が完全に曲がったまま固定され、趣味の写真撮影も仕事のパソコン操作もできなくなりました」と語っています。このように、ばね指の放置は思わぬ合併症や生活への影響をもたらす可能性があるのです。
ばね指の症状を感じたら、「様子を見よう」と放置せず、早めに医療機関を受診することをお勧めします。適切な時期の治療により、重症化を防ぎ、日常生活への影響を最小限に抑えることができます。
要注意!ばね指が重症化しているサイン
ばね指は初期段階で適切な治療を受ければ、比較的短期間で改善することが多い疾患です。しかし、症状を軽視して放置してしまうと、次第に症状が悪化し、日常生活に大きな支障をきたすようになります。この章では、ばね指が重症化している際に現れる警告サインについて詳しく解説します。
指が完全にロックして動かなくなる症状
ばね指の重症化で最も特徴的な症状は、指が特定の位置で「ロック」してしまう状態です。これは、腱鞘と腱の間の摩擦が極端に増加し、スムーズな滑りが完全に妨げられている状態を示しています。
初期段階では、朝起きた時など一時的に指が引っかかる程度でしたが、重症化すると次のような症状が現れます:
- 指を曲げた状態から自力で伸ばせなくなる
- 反対に、伸ばした状態から曲げられなくなる
- 指を動かすたびに強い痛みを伴う
- 指を無理に動かそうとすると、突然「バネ」のように跳ねるように動く
特に注意すべきは、朝起きた時だけでなく、日中の活動中にも指がロックする頻度が増えてきた場合です。このような状態になると、ボタンの留め外し、箸の使用、キーボード操作など、指先を使う細かい作業が著しく困難になります。
当院で診察した患者さんの中には、「最初は気にしていなかったが、いつの間にか指が完全に固まって動かせなくなり、反対の手の助けがなければ日常生活が送れなくなった」というケースも少なくありません。
| 重症度 | ロック症状の特徴 | 日常生活への影響 |
|---|---|---|
| 軽度 | 朝に一時的な引っかかり感がある | ほとんど支障なし |
| 中等度 | 日中も時々引っかかるが自力で解除可能 | 細かい作業に不便さを感じる |
| 重度 | 頻繁にロックし、自力での解除が困難 | 日常生活に大きな支障あり |
| 最重度 | 完全にロックして動かない | 基本的な手指の動作が不可能 |
激しい痛みや腫れが持続する場合
ばね指が重症化すると、単なる不快感や軽い痛みから、持続的で激しい痛みへと変化します。これは炎症が進行している明確なサインです。
重症化に伴う痛みの特徴として、以下のような症状が挙げられます:
- 指の付け根(MP関節付近)に鋭い痛みが常時存在する
- 夜間痛が生じ、睡眠を妨げるようになる
- 指を動かさなくても痛みを感じる
- 痛みが手のひらや前腕にまで広がる
また、腫れの症状も見逃せません。初期段階では軽度の腫れや違和感程度でしたが、重症化すると以下のような変化が表れます:
- 指の付け根に明らかな腫れや熱感がある
- 腫れた部分を押すと強い痛みがある
- 皮膚の色が赤みを帯びている
- しこりのような硬い腫れを触知できる
特に注意すべきは、これらの症状が一週間以上持続している場合です。一般的なばね指であれば、安静にすることで一時的に症状が軽減することがありますが、重症化したばね指では休息を取っても痛みや腫れが改善しにくくなります。
患者さんの中には「痛み止めを飲んでごまかしていたら、ある日突然指が動かなくなった」という方も多く、痛みを我慢して放置することは症状の悪化を招く原因となります。
手の機能が著しく低下したときの対処法
ばね指が重症化すると、指一本の問題にとどまらず、手全体の機能低下につながることがあります。これは日常生活の質を大きく下げる深刻な問題です。
手の機能低下を示す警告サインには以下のようなものがあります:
- 握力の著しい低下
- 物をつかむ動作が困難になる
- 手全体の使用を避けるようになる
- 他の指にも負担がかかり痛みが広がる
- 手首や腕全体に痛みやこわばりが生じる
このような症状が現れた場合の適切な対処法として、以下の点が重要です:
- すぐに整形外科を受診する 症状が進行している段階では、自己判断での対処は避け、専門医の診断を受けることが最優先です。当院では、重症化したばね指に対して適切な診断と治療方針の提案を行っています。
- 患部の安静を保つ 医療機関を受診するまでの間、できる限り患部に負担をかけないようにします。特に痛みを感じる動作は避け、必要に応じて市販の指サポーターなどで固定することも一時的な対処法として有効です。
- 冷却による炎症の抑制 腫れや熱感がある場合は、氷嚢などで10〜15分程度の冷却を行うことで、一時的に炎症を抑える効果が期待できます。ただし、冷却しすぎないよう注意が必要です。
- 痛みで眠れない場合の対策 夜間痛がひどい場合は、就寝時に患部を少し高くして寝る、または指サポーターで軽く固定することで、痛みを軽減できることがあります。
重症化したばね指による手の機能低下は、放置すればするほど回復に時間がかかるようになります。また、他の指に過度の負担がかかることで、新たなばね指を引き起こすリスクも高まります。
| 機能低下の程度 | 日常生活での具体的な支障 | 考えられるリスク |
|---|---|---|
| 軽度 | 細かい作業(ボタン留めなど)が少し困難 | 疲労感の増加 |
| 中等度 | 文字を書く、スマホ操作が困難 | 他の指への負担増加、仕事効率の低下 |
| 重度 | ドアノブを回せない、物を持てない | 日常生活全般の自立度低下、精神的ストレス |
| 最重度 | 手全体がほとんど使えない | 介助が必要、二次的な筋力低下、他の健康問題 |
当院での診療経験からも、「もう少し早く受診していれば」と後悔される患者さんが多いのが現実です。症状に気づいたら早めの受診をお勧めします。特に指がロックする、激しい痛みが続く、手の機能が低下したと感じる場合は、重症化している可能性が高いため、速やかな医療機関への相談が必要です。
早期発見・早期治療がカギ!ばね指の適切な診断方法
ばね指は初期段階で適切に対応すれば、重症化を防ぎ治療効果も高まります。しかし、多くの方が「単なる疲れか」と思い込んで放置してしまい、症状が悪化してから来院されるケースを日々診療で見かけます。この章では、ばね指を早期に発見し、適切な治療につなげるための診断方法について詳しく解説します。
どんな医療機関を受診すべきか
ばね指の症状に気づいたら、まずは整形外科を専門とする医療機関への受診をおすすめします。特に手の外科を専門としているクリニックであれば、より専門的な診断・治療が受けられる可能性が高まります。
整形外科のほか、以下のような医療機関でも診察を受けることができます:
| 医療機関 | 特徴 | メリット |
|---|---|---|
| 整形外科クリニック | 骨や関節、筋肉などの運動器を専門とする | ばね指の診断から治療まで一貫して対応可能 |
| 手外科専門クリニック | 手の疾患に特化した診療 | より高度な専門知識と治療技術 |
| リハビリテーション科 | 機能回復に焦点を当てた診療 | 保存療法やリハビリに強み |
| 総合病院 | 様々な診療科が連携 | 他の疾患との鑑別や合併症の対応が可能 |
初診時には以下の点に注意しましょう:
- 症状が出始めた時期や経過を正確に伝える
- 日常生活での動作や仕事での手の使い方を説明する
- これまでに試した対処法があれば伝える
- 他の持病や服用中の薬があれば必ず申告する
当院を含め多くの整形外科では、初診でも当日に診断から治療方針の提案まで行えることが一般的です。早期発見のためにも、「様子を見よう」と思わず、気になる症状があればすぐに専門医を受診することをお勧めします。
医師による診断の流れと検査内容
ばね指の診断は、主に問診と視診、触診を中心に行われます。検査の流れは以下のようになります。
問診
まず医師は以下のような点について詳しく質問します:
- いつから症状が始まったか
- どのような状況で痛みやひっかかり感が出るか
- 朝と夕方で症状に違いがあるか
- 手を使う仕事や趣味(楽器演奏、編み物など)があるか
- 過去に同様の症状を経験したことがあるか
- 糖尿病や関節リウマチなど関連疾患の有無
問診では症状の経過を時系列で伝えることが重要です。例えば「最初は朝だけ指が引っかかっていたが、最近は一日中症状がある」といった情報は、重症度の判断に役立ちます。
視診・触診
次に医師は以下のような検査を行います:
- 指の曲げ伸ばしの様子を観察
- 腱鞘(けんしょう)部分の腫れや熱感のチェック
- 手のひら側の付け根部分(A1プーリー)の圧痛の確認
- 指の動きに伴う「カクッ」という感覚の再現性確認
- 他の指との比較
医師は患者さんの指を直接触れて、腱の動きやひっかかりを確認します。この際、患者さん自身で再現できる症状があれば、積極的に医師に伝えることで正確な診断につながります。
画像検査
ばね指の診断において画像検査は必須ではありませんが、以下のような場合に補助的に行われることがあります:
- エコー検査:腱の肥厚や腱鞘の炎症状態を非侵襲的に確認できます
- レントゲン検査:骨の変形や関節の状態を確認し、他の疾患との鑑別に役立ちます
特にエコー検査は近年活用が増えており、腱鞘の肥厚や腱の状態をリアルタイムで視覚的に評価できる利点があります。当院でも必要に応じてエコー検査を実施し、より精度の高い診断に努めています。
重症度の判定基準について
ばね指の重症度は一般的に以下のような段階で評価されます:
| グレード | 症状 | 治療方針の目安 |
|---|---|---|
| グレード1(軽症) | 指の動きに違和感があるが、引っかかりはない。腱鞘部分に軽い痛みがある | 保存療法が中心(安静、固定、消炎鎮痛剤など) |
| グレード2(中等症) | 指を曲げ伸ばしする際に引っかかり感があるが、自力で動かせる | 保存療法に加え、ステロイド注射を検討 |
| グレード3(重症) | 指がロックし、自力での伸展が困難。他の指や反対の手の助けが必要 | ステロイド注射、効果がなければ手術を検討 |
| グレード4(最重症) | 指が固定され、曲げ伸ばしがほぼ不可能になった状態 | 多くの場合、手術療法が必要 |
この分類は医療機関によって若干の違いがあることもありますが、基本的な考え方は共通しています。重症度判定の際に重要なポイントは以下の通りです:
- ひっかかりの頻度(時々か常にか)
- 自力で指を伸ばせるかどうか
- 痛みの程度と持続時間
- 日常生活への支障の度合い
- 症状の進行スピード
重症度が高いほど治療の難易度が上がり、回復までの期間も長くなる傾向があります。そのため、グレード1〜2の段階で適切な治療を開始することが理想的です。
自己チェックで重症度を把握する方法
医療機関を受診する前に、自分でおおよその重症度を確認するには以下のチェックポイントが参考になります:
- 朝起きた時に指の動きが悪いことがあるか
- 指を曲げた状態から伸ばす時に「カクッ」という感覚があるか
- 指の付け根の手のひら側を押すと痛みがあるか
- 指を完全に伸ばせないことがあるか
- 日常生活の動作(ボタンかけ、包丁使用など)に支障をきたしているか
これらの項目に該当する数が多いほど重症度が高い可能性があります。特に3つ以上当てはまる場合は早急に専門医の診察を受けることをお勧めします。
当院では、患者さんの症状や生活背景を詳しく伺った上で、個々の状況に最適な治療法をご提案しています。ばね指は早期発見・早期治療が何よりも重要な疾患です。少しでも気になる症状があれば、遠慮なくご相談ください。
重症化したばね指の治療法と回復への道筋
ばね指が重症化すると、日常生活に大きな支障をきたすようになります。指が完全にロックしてしまったり、強い痛みが持続したりする状態では、適切な治療を受ける必要があります。当院では重症度に応じた段階的な治療アプローチを提案しています。ここでは重症化したばね指の治療法と回復までの道のりについて詳しく解説します。
保存療法:安静・固定・薬物治療の効果
重症化したばね指であっても、まずは保存療法から始めることが一般的です。保存療法とは、手術をせずに症状の改善を目指す治療法です。
指の安静と固定は基本的な対処法です。腱鞘の炎症を抑えるためには、指の動きを一時的に制限することが効果的です。専用のスプリント(固定具)を使用して、問題のある指を数週間固定します。特に夜間の装着は、睡眠中の無意識な指の動きによる刺激を防ぐ効果があります。
薬物治療では、非ステロイド性抗炎症薬(湿布や内服薬)を用いて、炎症と痛みを抑える治療を行います。これらの薬剤は腱鞘の腫れや炎症を抑制する効果がありますが、根本的な解決にはならないケースも少なくありません。
| 保存療法の種類 | 期待される効果 | 治療期間の目安 |
|---|---|---|
| スプリント固定 | 腱鞘への負担軽減、炎症の沈静化 | 2〜6週間 |
| 抗炎症薬(内服) | 痛みの軽減、炎症の抑制 | 1〜2週間 |
| 抗炎症薬(外用) | 局所的な炎症の抑制 | 2〜4週間 |
| アイシング | 急性期の痛みや腫れの軽減 | 症状に応じて(1日数回) |
しかし、重症化したばね指では、これらの保存療法だけでは十分な効果が得られないことも少なくありません。特に完全に指がロックしてしまっている状態や、長期間症状が続いている場合は、次のステップの治療を検討する必要があります。
ステロイド注射による治療とその有効性
保存療法で改善が見られない場合、ステロイド注射療法を検討します。これは腱鞘内にステロイド剤を直接注入することで、強い抗炎症効果を発揮させる治療法です。
ステロイド注射は、重症化したばね指に対して高い効果を示すことが多く、多くの患者さんが1回の注射で症状の改善を実感されます。腱鞘の腫れや炎症を強力に抑え、指の動きをスムーズにする効果があります。
ステロイド注射の有効率は、軽度から中等度のばね指では約70〜80%と言われていますが、重症例では効果が限定的になることもあります。また、複数の指にばね指が生じている場合や、糖尿病の方では効果が出にくいことがあります。
注射後は一時的に痛みが増すことがありますが、数日で落ち着くことが多いです。効果の持続期間は個人差がありますが、3か月から半年程度持続することが期待できます。
ただし、ステロイド注射にも限界があります。注射の回数が増えると効果が徐々に減弱することや、腱の脆弱化などの副作用のリスクが高まることが知られています。一般的には、同じ部位への注射は3回程度までとされています。
| ステロイド注射の特徴 | 詳細 |
|---|---|
| 効果の発現時期 | 数日〜2週間程度 |
| 効果の持続期間 | 3か月〜半年程度(個人差あり) |
| 推奨される最大注射回数 | 同一部位に3回程度まで |
| 主な副作用 | 一時的な痛み、皮下組織の萎縮、腱の脆弱化(頻度は低い) |
当院では、ステロイド注射を行った後も経過観察を丁寧に行い、効果が不十分な場合は次の治療ステップを提案しています。
手術療法が必要となるケースと手術方法
保存療法やステロイド注射で十分な改善が見られない重症のばね指では、手術療法が検討されます。特に以下のような状況では手術が推奨されることがあります。
- 3か月以上の保存療法で改善しない場合
- ステロイド注射を2〜3回行っても再発する場合
- 指が完全にロックして自力で伸ばせない状態が続く場合
- 日常生活に著しい支障をきたしている場合
手術の目的は、腱鞘を切開して滑走障害を解消することです。具体的には、腱とその周囲の腱鞘との間で起こっている引っかかりを解消するために、腱鞘を部分的に切開します。これにより、腱がスムーズに動けるようになります。
従来の手術方法と最新の低侵襲手術
ばね指の手術方法には、大きく分けて従来の開放手術法と、より低侵襲な方法があります。
従来の開放手術法は、局所麻酔をして患部に1〜2cm程度の皮膚切開を行い、直接腱鞘を確認して切開する方法です。手術時間は15〜20分程度で、確実に腱鞘を解放できる利点があります。
近年では、より傷が小さく済む低侵襲手術も行われるようになってきました。これは、特殊な器具を使用して、より小さな切開で腱鞘を切開する方法です。傷が小さいため、術後の痛みが少なく、回復が早いという利点があります。
また、各施設で様々な工夫がなされており、エコー(超音波)ガイド下で行うテクニックなど、新しいアプローチも開発されています。
| 手術方法 | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 従来の開放手術 | 1〜2cmの皮膚切開 | 直視下で確実な腱鞘切開が可能 | 創部がやや大きい |
| 低侵襲手術 | より小さな切開 | 術後痛みが少なく、回復が早い | 技術的に難しいことがある |
| エコーガイド下手術 | 超音波で確認しながら実施 | 周囲組織の損傷を最小限に | 特殊な機器と技術が必要 |
手術方法の選択は、患者さんの状態や医師の専門性によって異なります。当院では患者さん一人ひとりの状態に合わせた最適な治療法を提案しています。
手術後のリハビリテーションと回復期間
手術後は適切なリハビリテーションが重要です。術後の回復過程と、各段階でのリハビリの内容を理解しておくことで、より効果的に機能回復を進めることができます。
手術直後から1週間程度は創部の保護が最優先です。傷口を清潔に保ち、指示された範囲で軽い動きを行います。過度な力を入れる動作は避ける必要があります。
抜糸後(通常は術後10〜14日程度)からは、より積極的な指の運動を始めることができます。この時期からは、腱の滑走をスムーズにするためのリハビリテーションが重要になります。
術後2〜4週間は、日常生活動作への復帰期間です。この時期には腱の滑走性を高めるための指の屈伸運動や、握力を徐々に回復させるためのトレーニングを行います。ただし、力仕事や重いものを持つなどの負荷のかかる動作は、4〜6週間は控えることが推奨されます。
手術後のリハビリテーションスケジュールの一例を以下に示します。
| 術後期間 | リハビリ内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 術後1〜3日 | 術部の安静と保護、軽い自動運動 | 傷口を濡らさない、過度な動きを避ける |
| 術後3日〜1週間 | 軽い屈伸運動の開始 | 痛みの範囲内で行う |
| 術後1〜2週間 | 抜糸、日常的な軽作業の再開 | 創部の過度な牽引を避ける |
| 術後2〜4週間 | 指の柔軟性と握力の回復訓練 | 徐々に負荷を増やす |
| 術後4〜6週間 | ほぼ通常の使用が可能に | 強い握力や長時間の使用は控える |
| 術後6週間以降 | ほとんどの活動に制限なし | 再発防止のためのケアを継続 |
手術後の経過は個人差があり、年齢や症状の重症度、手術前の状態などによって回復速度が異なります。高齢の方や、長期間症状が続いていた方、複数の指に症状がある方などは、回復に時間がかかることがあります。
また、糖尿病や甲状腺疾患などの基礎疾患がある方は、治療効果や回復期間に影響することがあります。こうした場合は、より慎重なフォローアップが必要です。
手術後の定期的な通院とリハビリテーションを通じて、医師や理学療法士による専門的なアドバイスを受けながら回復を進めることが、最も良い結果につながります。
当院では手術後も丁寧な経過観察を行い、患者さんの回復状況に合わせたリハビリプログラムを提供しています。また、日常生活でのセルフケアの方法や、再発予防のためのアドバイスも行っています。
ばね指の重症化を予防するためのセルフケア
ばね指は早期に適切なケアを行うことで、重症化を防げる可能性が高い疾患です。日常生活でのちょっとした工夫や、正しいセルフケアの知識を身につけることで、症状の進行を遅らせたり、再発を防いだりすることができます。この章では、自分でできるばね指のケア方法について詳しく解説します。
日常生活での指の負担を減らす工夫
ばね指の予防や悪化防止には、まず日常生活での指への負担を軽減することが重要です。特に症状が出始めた場合は、以下のような工夫を意識して取り入れましょう。
繰り返し同じ動作を長時間続けることは避けるようにしましょう。特にスマートフォンの長時間使用、園芸作業、編み物、調理など、指に負担がかかる作業は適度に休憩を入れることが大切です。
また、日常生活では以下の点に注意することで、指への負担を減らすことができます:
- 重い荷物を持つときは、指だけでなく手のひら全体や両手を使う
- 細かい作業をするときは、ergonomic(人間工学に基づいた)設計の道具を選ぶ
- パソコン作業が多い方は、手首と指に負担がかからないキーボードやマウスを使用する
- スマートフォンの操作は親指だけでなく、人差し指なども使い分ける
- 調理の際は、握りやすい太めの柄のある包丁や調理器具を選ぶ
症状がある時には、指の安静を保つためにスプリント(指サポーター)を使用することも効果的です。市販のものでも構いませんが、症状に合ったものを医療機関で相談することをお勧めします。
| 日常動作 | 指への負担 | 負担軽減のための工夫 |
|---|---|---|
| スマートフォン操作 | 親指の付け根に大きな負担 | 両手持ちで操作、音声入力の活用、休憩を定期的に入れる |
| キーボード入力 | 指の繰り返し動作による負担 | リストレスト使用、正しい指の位置、1時間に5分の休憩 |
| 調理作業 | 包丁や調理器具による指への負担 | 握りやすいハンドルの調理器具使用、適度な休憩 |
| 掃除・洗濯 | 絞る動作や力を入れる動作 | 雑巾は強く絞らない、洗濯物は少量ずつ |
| 趣味(編み物・園芸など) | 細かい動作の繰り返し | 30分ごとに休憩、手袋の着用、適切な道具選び |
効果的なストレッチと自己マッサージ法
定期的なストレッチや適切なマッサージは、ばね指の予防や症状の軽減に役立ちます。ただし、痛みを感じる場合は無理にストレッチを行わず、医師に相談することが重要です。以下に、安全で効果的なストレッチとマッサージ法をご紹介します。
基本的な指のストレッチ
次のストレッチを1日2〜3回、各5〜10回ずつ行うことで、指の柔軟性を保ち、腱鞘への負担を軽減できます。
- 指広げストレッチ:手のひらを上に向け、指をゆっくりと大きく広げます。5秒間保持し、ゆっくりと元に戻します。
- 指曲げストレッチ:手のひらを上に向け、指を一本ずつゆっくりと曲げて手のひらに触れるようにします。各指で5秒間保持し、ゆっくりと戻します。
- 手首回しストレッチ:手を軽く握り、手首をゆっくりと時計回りと反時計回りに5回ずつ回します。
- 親指ストレッチ:親指をゆっくりと大きく円を描くように動かします。時計回りと反時計回りに5回ずつ行います。
効果的な自己マッサージ法
マッサージは血行を促進し、腱の動きをスムーズにするのに役立ちます。以下のマッサージ法を1日2回程度、痛みのない範囲で行いましょう。
- 手のひらマッサージ:反対の手の親指で、症状のある指の付け根(手のひら側)を優しく円を描くようにマッサージします。約1分間行います。
- 指全体のマッサージ:症状のある指を根元から指先に向かって、もう片方の手で包み込むようにやさしくマッサージします。
- 腱に沿ったマッサージ:手のひらから指に伸びる腱に沿って、軽く圧をかけながら指先に向かってマッサージします。
マッサージを行う際の注意点として、強い痛みを感じる場合は即座に中止し、炎症がある場合(熱感・強い腫れ・激しい痛み)はマッサージを避けてください。こうした症状がある場合は、医療機関での適切な処置が必要です。
温冷療法の活用
症状に応じた温冷療法も効果的です:
- 冷却療法:急性期や炎症がある場合は、氷水に浸したタオルなどで10〜15分間、患部を冷やします。皮膚を保護するためにタオルで包んだ氷嚢を使用するとよいでしょう。
- 温熱療法:慢性期や朝のこわばりがある場合は、ぬるま湯で手を温めたり、蒸しタオルを当てたりすると、血行が促進され症状が和らぐことがあります。38〜40度程度の温度で10〜15分間行います。
再発防止のための生活習慣の見直し
ばね指は一度発症すると再発しやすい傾向があります。長期的な予防と管理のためには、生活習慣全体を見直すことが重要です。
適切な休息と活動のバランス
過度の使用と完全な不使用のどちらも指に良くありません。適切なバランスを保つことが重要です:
- 同じ動作を長時間続けない(1時間に5分程度は休憩を入れる)
- 痛みを感じたら早めに休息を取る
- 就寝時や長時間の作業時はサポーターを使用する
- 症状がない時期も、予防的にストレッチを継続する
全身の健康管理
ばね指の予防には、手指だけでなく全身の健康管理も重要です:
- 適正体重の維持:過体重は手の関節にも負担をかけることがあります
- 水分摂取:十分な水分補給は関節の潤滑にも役立ちます
- バランスの良い食事:抗炎症作用のある食品(青魚、オリーブオイル、クルミなど)や、コラーゲン生成を助ける栄養素(ビタミンCを含む果物や野菜)を積極的に摂りましょう
- 喫煙の回避:喫煙は血行不良を引き起こし、治癒を遅らせることがあります
職場環境の改善
特に仕事で手を多用する方は、職場環境の見直しも重要です:
- 人間工学に基づいたキーボード、マウス、工具などを使用する
- デスクや作業台の高さを適切に調整する
- 長時間の同じ姿勢や動作を避け、定期的に姿勢を変える
- 可能であれば、作業の種類を日中に変えて、同じ動作の繰り返しを減らす
症状が出始めたら早めの受診が重要です。「様子を見よう」と放置することで症状が悪化し、治療が長引くことがあります。軽度のうちに適切な処置を受けることで、重症化を防ぎ、早期回復が期待できます。
定期的なセルフチェック
予防の観点から、定期的に以下のようなセルフチェックを行うことをお勧めします:
| チェックポイント | 正常な状態 | 注意が必要な状態 |
|---|---|---|
| 朝の指の動き | スムーズに曲げ伸ひ可能 | こわばりや引っかかりを感じる |
| 指の腫れ | 腫れがない | 指の付け根や関節部分の腫れ |
| 痛み | 痛みがない | 指を動かした時や押した時の痛み |
| クリック音 | 音がしない | 指を曲げ伸ばし時のカクカク音 |
| 握力 | しっかり握れる | 握る力が弱くなった感覚 |
これらのセルフケア方法を日常生活に取り入れることで、ばね指の予防や症状の軽減が期待できます。しかし、セルフケアだけでは改善が見られない場合や、症状が悪化している場合は、速やかに整形外科を受診しましょう。専門医による適切な診断と治療が、ばね指の重症化を防ぐ最も確実な方法です。
ばね指と間違えやすい手指の疾患との違い
ばね指の症状は他の手指の疾患と似ていることがあるため、正確な診断には専門医の診察が欠かせません。症状が似ている他の疾患と区別できることで、より適切な治療につながります。
腱鞘炎や手根管症候群との症状の違い
ばね指と最も間違えやすいのが腱鞘炎です。どちらも指や手の痛みを伴いますが、決定的な違いがあります。
| 疾患 | 主な症状 | 発症部位 | 特徴的な症状 |
|---|---|---|---|
| ばね指 | 指を曲げ伸ばしする際の引っかかり感、バネのような動き | 主に親指、中指、薬指のMP関節付近 | 朝に症状が悪化、指の付け根に痛みと腫れを伴うしこり |
| 腱鞘炎 | 持続的な痛みとこわばり | 手首や指全体に広がることが多い | 動かすたびに痛みが出るが、ばね指特有の引っかかりはない |
| 手根管症候群 | 手のしびれ、痛み、脱力感 | 親指から中指にかけての手のひら側 | 夜間に痛みが悪化、指先のしびれ、物を落としやすい |
手根管症候群は特に間違えやすい疾患です。手根管症候群では正中神経の圧迫により、主に夜間のしびれや痺れ感が特徴的です。手根管症候群では指の曲げ伸ばしでの引っかかり感がなく、むしろ感覚障害が主症状となります。
腱鞘炎の場合、ドケルバン病と呼ばれる親指の付け根の腱鞘炎が有名です。この場合、親指を動かすと痛みが出ますが、ばね指のように指が引っかかったり、ロックしたりする症状はありません。
また、ばね指では朝方に症状が悪化することが多いですが、腱鞘炎は使い続けると痛みが増す傾向にあります。腱鞘炎はより広範囲に痛みが広がり、特定の指の付け根に明確なしこりを触れることが少ないという違いもあります。
関節リウマチとの区別ポイント
関節リウマチもばね指と似た症状を示すことがありますが、病態は大きく異なります。
関節リウマチは自己免疫疾患であり、炎症が体内の複数の関節に同時に現れることが特徴です。一方、ばね指は使いすぎによる機械的な問題から生じる局所的な症状です。
| 区別ポイント | ばね指 | 関節リウマチ |
|---|---|---|
| 症状の対称性 | 通常は片方の手の1〜2本の指に発症 | 左右対称に複数の関節に症状が出やすい |
| 朝のこわばり | 短時間(数分程度)で改善することが多い | 1時間以上続くことが多い |
| 関節の変形 | 通常は関節変形を伴わない | 進行すると関節変形が見られる |
| 全身症状 | 全身症状はない | 発熱、倦怠感、体重減少などを伴うことがある |
| 検査所見 | 血液検査で炎症マーカーは通常正常 | リウマトイド因子、抗CCP抗体陽性、炎症マーカー上昇 |
関節リウマチでは朝のこわばりがより長時間続き、複数の関節に同時に症状が出現することが多いです。また、関節リウマチでは関節の痛みや腫れに加えて、全身倦怠感や微熱などの全身症状を伴うことがあります。
当院では、リウマチの可能性がある場合は血液検査を行い、リウマトイド因子や抗CCP抗体の有無を確認します。また、必要に応じて手指のエコー検査を行い、腱鞘の状態や滑膜の肥厚の程度を評価します。
変形性関節症との鑑別ポイント
加齢とともに増えてくる変形性関節症も、ばね指と間違えやすい疾患の一つです。
変形性関節症は軟骨のすり減りによって起こる疾患で、特にヘバーデン結節やブシャール結節と呼ばれる指の第一関節や第二関節のこぶが特徴的です。
| 特徴 | ばね指 | 変形性関節症 |
|---|---|---|
| 主な発症部位 | MP関節(指の付け根) | DIP関節(指先の関節)、PIP関節(指の真ん中の関節) |
| 年齢層 | 30〜50代に多い | 50代以降の高齢者に多い |
| 痛みの性質 | 動かした時の引っかかりと痛み | じわじわとした痛み、天候の変化で悪化 |
| 見た目の変化 | 指の付け根に軽度の腫れやしこり | 関節の明らかな変形やこぶ |
変形性関節症では指の第一関節や第二関節に硬いこぶができ、関節の変形が見られますが、ばね指特有の引っかかり感はありません。また、レントゲン検査では変形性関節症では関節裂隙の狭小化や骨棘形成といった特徴的な所見が見られます。
当院ではエコー検査で腱鞘の肥厚を確認することで、ばね指の診断を確定させています。変形性関節症とばね指は治療法が異なるため、正確な鑑別診断が重要です。
デュピュイトラン拘縮との違い
特に中高年の男性に多いデュピュイトラン拘縮も、指の曲がりに関する症状があるため、ばね指と混同されることがあります。
デュピュイトラン拘縮は手のひらの筋膜(腱膜)が肥厚・拘縮することで、指が徐々に曲がり、伸ばせなくなる疾患です。一方、ばね指は指を曲げる際の引っかかりが特徴です。
| 特徴 | ばね指 | デュピュイトラン拘縮 |
|---|---|---|
| 発症部位 | 指の付け根(MP関節) | 手のひらから小指や薬指側 |
| 症状の進行 | 比較的急速に症状が現れることが多い | ゆっくりと年単位で進行する |
| 特徴的な所見 | 指の付け根のしこりと引っかかり感 | 手のひらの皮膚が硬くなり、索状の硬い組織が触れる |
| 指の状態 | 指は引っかかりがあるが、無理すれば伸ばせる | 進行すると完全に伸ばせなくなる |
デュピュイトラン拘縮では手のひらに索状の硬い組織(腱索)が触れ、徐々に指が曲がっていくのに対し、ばね指では指の曲げ伸ばし時のカクカクとした動きが特徴的です。デュピュイトラン拘縮はアルコール多飲、糖尿病、喫煙などと関連があるとされています。
当院では、手のひらの皮膚の状態や指の可動域を詳細に確認し、適切な診断を行っています。特に両疾患が合併している場合は、それぞれに適した治療計画を立てることが重要です。
神経麻痺による指の障害との鑑別
手や指の神経麻痺によって生じる症状も、ばね指と間違えられることがあります。特に尺骨神経麻痺や正中神経麻痺は、指の動きに障害を引き起こします。
神経麻痺では、指の動きのぎこちなさや力が入りにくいといった症状が主体ですが、ばね指のような引っかかり感は通常見られません。
| 神経麻痺の種類 | 主な症状 | ばね指との違い |
|---|---|---|
| 尺骨神経麻痺 | 小指と薬指の感覚障害、手の筋力低下、鷲手変形 | 引っかかり感はなく、しびれや脱力が主症状 |
| 正中神経麻痺 | 親指から中指の感覚障害、猿手変形 | 指先のしびれが特徴的で、曲げ伸ばし時の痛みは少ない |
| 橈骨神経麻痺 | 手首や指を伸ばす力の低下(垂れ手) | 指を伸ばす力が弱くなるが、ばね現象はない |
神経麻痺による症状では筋力低下やしびれが主体となり、ばね指特有の指の引っかかり感や弾発現象は見られません。また神経麻痺では通常、感覚障害(しびれや感覚鈍麻)を伴うことが多いです。
当院では神経学的検査を丁寧に行い、筋力や感覚の評価、反射の確認などを通じて神経麻痺とばね指の鑑別を行っています。必要に応じて神経伝導速度検査などの精密検査をご案内することもあります。
ばね指は適切な治療を行えば比較的短期間で改善することが多いですが、神経麻痺の場合は原因や重症度によって治療法や回復期間が大きく異なります。そのため、正確な診断が非常に重要となります。
体験者の声:ばね指を放置して後悔した実例と教訓
ばね指の症状を放置することで、どのような結果につながるのか。実際に経験された方々の声から、その教訓を学ぶことができます。当院で診察させていただいた患者さんの実例をもとに、症状の進行と対処法について紹介します。
「痛みに慣れてしまった」重症化までの体験談
50代女性のAさんは、料理が趣味で毎日欠かさず家族のために手の込んだ料理を作っていました。最初は朝起きた時に親指の付け根に軽い違和感を感じる程度でした。
「最初は、歳のせいだと思って気にしていませんでした。少し痛いけれど、日常生活に支障はなかったんです。でも、徐々に指が引っかかる感じが出てきて…」とAさん。
症状が出始めてから約3ヶ月間、特に治療せずに過ごしたことで、ある朝突然、親指が曲がったまま戻らなくなりました。
「痛みで目が覚めたんです。親指が曲がったままで、無理に伸ばそうとすると激痛が走る。慌てて病院に駆け込みました」
初期症状を放置したことで、Aさんの場合は腱鞘の炎症が進行し、指が完全にロックする重症のばね指に発展していました。結果的に日常生活に大きな支障をきたし、ステロイド注射による治療が必要になりました。
また、60代男性のBさんは趣味の大工仕事でのこぎりや金づちを頻繁に使用していました。
「中指と薬指にカクッという引っかかりを感じましたが、休めば治ると思って1年近く我慢していました。徐々に痛みが強くなり、夜も痛みで眠れないほどになったんです」
Bさんは複数の指に症状が現れ、特に朝方の痛みがひどくなったことで日常生活に大きな制限を感じるようになりました。
| 放置期間 | 症状の進行 | 生活への影響 |
|---|---|---|
| 1〜3ヶ月 | 軽い引っかかり感から痛みを伴う引っかかりへ | 細かい作業が少し困難に |
| 3〜6ヶ月 | 朝のこわばりが長時間続く、常時痛みを感じる | 家事や仕事に支障が出始める |
| 6ヶ月以上 | 指のロック現象が頻発、強い痛みが持続 | 日常生活全般に大きな支障 |
「もっと早く受診していれば、こんなに苦労しなかったのに」というのがBさんの後悔です。
30代主婦のCさんは、小さな子供の育児と家事に追われる毎日でした。右手の中指に症状が出始めた頃は、育児の忙しさから「そのうち治る」と考えていました。
「赤ちゃんのおむつ替えやミルクの準備など、指を使う動作が多いので、痛みがあっても構っていられなかったんです。でも、子供を抱き上げる時に指に激痛が走って、危うく落としそうになったことがきっかけで受診しました」
Cさんの場合、症状を放置したことで、育児という大切な役割にも影響が出始めていました。早期に適切な治療を受けていれば、短期間で改善できた可能性があります。
早期治療で改善した方々の成功事例
一方で、早期に症状に気づき適切な治療を受けた方々は、比較的短期間で日常生活に復帰されています。
40代会社員のDさんは、デスクワークが中心の仕事で、キーボード入力が多い日々を送っていました。右手の人差し指に違和感を感じた際、すぐに整形外科を受診しました。
「同僚がばね指で苦労していたのを見ていたので、似たような症状を感じたらすぐに病院に行こうと決めていました。診断は初期のばね指でした」
Dさんの場合、早期発見により保存療法で症状が改善。専用のサポーターで固定し、仕事の合間に適切なストレッチを行うことで、約2週間で症状が軽減しました。
早期発見・早期治療の重要性は、回復期間の短縮だけでなく、治療の負担軽減にもつながります。重症化してからの治療に比べ、痛みや経済的・時間的コストも大幅に削減できるのです。
50代パート勤務のEさんは、スーパーのレジ係として働いていました。商品をスキャンする作業で中指に違和感を感じ始め、1週間ほどで受診されました。
「職場の先輩に相談したら、『ばね指かもしれないから早めに病院へ行った方がいい』とアドバイスをもらいました。本当に感謝しています」
Eさんは初期症状の段階で適切な処置を受け、仕事の調整と自宅でのケアを続けることで、約1ヶ月で完全に症状が消失しました。
| 早期治療のメリット | 具体的な効果 |
|---|---|
| 痛みの軽減期間 | 重症化した場合の1/3〜1/2の期間で改善 |
| 治療の侵襲性 | 保存療法で改善する可能性が高い |
| 日常生活への影響 | 大きな制限なく生活できることが多い |
| 再発リスク | 適切なセルフケアを学ぶことで再発予防が可能 |
実際に多くの患者さんが「もっと早く受診していれば」と後悔されています。特に初期症状が出た段階で適切な対応ができれば、重症化を防ぎ、より簡単な治療で済む可能性が高まります。
70代のFさんは、初期症状に気づいてすぐに受診された方です。
「年齢的に手の不調は様々ありますが、今回は明らかに違う症状だったので迷わず受診しました。医師からは『早めの受診で良かった』と言ってもらえました」
Fさんは適切なタイミングでの受診により、短期間の固定とストレッチ指導だけで症状が改善。高齢であっても、早期対応によって良好な結果が得られた好例です。
これらの体験者の声から学べることは、「違和感や痛みを我慢せず、早めに専門医に相談する」という基本的な姿勢の重要性です。ばね指は適切な時期に適切な治療を受けることで、多くの場合、良好な経過をたどります。
日々の生活で指に違和感を感じたら、「様子を見よう」という判断を長引かせず、専門医への相談を検討してみてください。早期発見・早期治療が、あなたの指の健康を守る最善の方法です。
まとめ:ばね指の重症化を防ぐために今すぐできること
ばね指は早期発見・早期治療が何よりも重要です。初期段階で違和感や軽い引っかかりを感じたら、整形外科を受診しましょう。日常生活では、指に負担をかける動作を控え、ロキソニンなどの消炎鎮痛剤で炎症を抑えることも一時的な対処として有効です。また、適切なストレッチや休息を取り入れ、スマートフォンの長時間使用やきつい握り動作を避けることで予防にもつながります。重症化すると手術が必要になるケースもあるため、「様子を見よう」と放置せず、症状に合わせた適切な治療を受けることが回復への近道です。痛みが取れない、違和感があるなどお困りごとがありましたら当院へご相談ください。