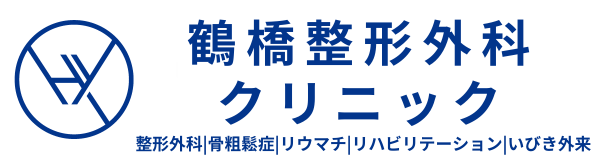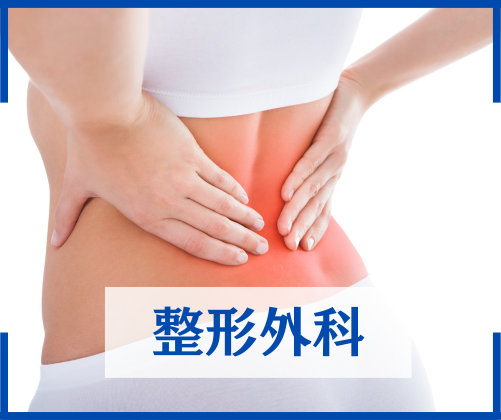膝の横が曲げると痛む原因は半月板損傷や腸脛靱帯炎など部位で異なります。本記事では医師監修の診断法・RICE処置・リハビリ・手術適応・再発予防までを網羅解説し、症状に応じた最適な対処と受診タイミングが分かります。結論、痛みを放置せず負荷軽減と専門医の早期診断が回復の鍵です。自宅でできるストレッチ動画へのリンクやサポーター選びのコツも紹介するので、スポーツ愛好家から高齢者まで安心して実践できます。
膝の横が痛いときの特徴と曲げると痛い症状
痛みが現れやすい動作
膝を深く曲げた瞬間に鋭い痛みが走ることが多く、正座やしゃがみ込み、階段の上り下りで症状が明確になります。特に下り階段では体重が膝の外側・内側に集中するため、「踏み出した瞬間に力が抜けるような痛み」を訴える患者さまがよくいらっしゃいます。
また、イスから立ち上がる、車の乗り降りなど日常生活の動作でも痛みが出やすく、仕事で長時間の立ち姿勢や中腰姿勢を強いられる方は夕方に痛みが増幅する傾向があります。
痛みの性質と随伴するサイン
痛みは刺すような痛みからにぶい鈍痛まで幅がありますが、共通して「膝を伸ばすとやや軽減し、再度曲げ始めると増強する」というリズムを示します。腫れや熱感を伴うケースは急性炎症が疑われ、動かすたびにコキッという音や引っかかり感がある場合は軟骨や半月板の損傷が背景に隠れていることがあります。
時間帯・気候と痛みの関係
朝起きてすぐはこわばりが強く、動かすうちにほぐれていくものの、夕方の帰宅時や入浴後に再び痛みが増す方が多いのが特徴です。梅雨時や冬場など気圧や気温が急激に変化する日は膝の外側・内側ともに痛みが悪化しやすいため、当院でも来院が増える傾向があります。
外側と内側で異なる症状の例
| 部位 | 主な自覚症状 | 痛みが強まる場面 |
|---|---|---|
| 外側 | 膝の外くるぶし付近まで響く突っ張り感、歩行開始時の鋭い痛み | 長距離歩行、坂道の下り、ランニング後半 |
| 内側 | 膝のお皿の内側下方がじんじんと重だるい、押すと局所的に痛む | 正座、和式トイレでの屈伸、長時間の立ちっぱなし |
鶴橋整形外科クリニックでよく受診される年代と傾向
二十代のスポーツ愛好家は外側痛が、四十代以降の立ち仕事の方は内側痛が多いという傾向があります。高齢の患者さまでは筋力低下や体重増加が重なり、「曲げ伸ばしのたびにギクッと痛む」と表現される例が目立ちます。当院では症状の出方と生活背景を丁寧に伺うことで、原因を絞り込み、適切な対応策をご提案しています。
主な原因
膝の横に痛みが出て曲げる動作で強まる場合、痛みの位置(外側か内側か)と発症状況から原因を大きく三つに分類できます。当院ではまず「どこが、どの動きで、いつから痛むか」を丁寧に伺い、下記の疾患や生活習慣との関連を確認します。
外側か内側かで異なる代表的な疾患
| 痛む部位 | 主な疾患 | 特徴的な症状 | 好発場面 |
|---|---|---|---|
| 外側 | 腸脛靭帯炎 外側半月板損傷 外側側副靭帯損傷 | 膝を曲げ伸ばしするたびに外側が擦れるような痛み 荷重時の不安定感 | 長時間のランニングや階段昇降 急な方向転換 |
| 内側 | 変形性膝関節症 内側半月板損傷 鵞足炎 | 動き始めの疼痛・こわばり 正座やしゃがみ込みで鋭い痛み | 加齢に伴う軟骨変性 膝をひねる動作・急停止 |
外側の痛み: 腸脛靭帯炎・外側半月板損傷・外側側副靭帯損傷
腸脛靭帯炎は、太ももの外側を走る腸脛靭帯が膝の骨と擦れ合い炎症を起こす疾患です。走行距離の急増や硬い路面での長時間歩行がきっかけとなりやすく、曲げ伸ばし時に「カクッ」と引っ掛かる感覚を伴うこともあります。
外側半月板損傷は、膝をひねった際に半月板が裂けたり亀裂が入ったりして起こります。痛みと共に可動域制限や膝折れ感が出るため、スポーツ活動を続けるほど悪化しやすいのが特徴です。
外側側副靭帯損傷は横からの衝撃で靭帯が伸びたり部分断裂したりする外傷性の疾患です。腫れが強く、体重をかけると外側が抜けるような不安定感がみられます。
内側の痛み: 変形性膝関節症・内側半月板損傷・鵞足炎
変形性膝関節症では、加齢や体重増加により関節軟骨がすり減り、内側に負担が集中して痛みを生じます。朝のこわばりや階段下降時の疼痛が出やすく、進行するとO脚傾向が強まります。
内側半月板損傷は、ひねり動作や深い屈伸で半月板が挟み込まれて損傷することで起こります。損傷部位が大きいと膝が途中で動かなくなる「ロッキング現象」を伴うこともあります。
鵞足炎は、膝の内側下部で筋腱が骨とこすれて炎症を起こす疾患です。正座や階段昇降で鋭い痛みが走り、触れると熱感があります。中高年の女性や長距離ランナーに多い傾向です。
スポーツや日常生活の負荷による原因
疾患名が特定できない場合でも、過度な運動量・硬い路面でのジョギング・急な体重増加・合わない靴などが複合的に関与し、膝の内外側に炎症を起こすことがあります。また、長時間のデスクワークで膝が曲がったまま固まる姿勢や、和式トイレ・正座など深い屈伸を繰り返す生活習慣も痛みを誘発します。
鶴橋整形外科クリニックでは、問診で運動歴・職業・日常動作を細かく伺い、レントゲンや超音波検査を組み合わせて原因を絞り込みます。痛みを感じた時点で早めに受診いただくことで、慢性化や変形の進行を防ぐことができます。
整形外科での診断と検査方法
問診・視診・触診で分かるポイント
鶴橋整形外科クリニックでは、患者さまの訴えを詳細に伺う問診が診断の第一歩です。受傷した状況や痛みが出る動作、職業・スポーツ歴、既往歴を把握することで、外側か内側か、あるいは前後面なのかを推定できます。
続いて視診を行い、膝の腫れ・熱感・皮下出血の有無を確認します。腫脹が強い場合は関節内の炎症や血腫を疑い、左右差の比較で変形性変化の進行度も評価します。
触診では、痛みの出る部位を指先で丁寧に押さえ、圧痛点を特定します。外側の腸脛靭帯上や内側の鵞足部に明確な圧痛があるかどうかで、靭帯炎・腱付着部炎の可能性を絞り込みます。
さらに、膝の可動域検査を実施し、曲げ伸ばしで痛みが増強する角度や制限される角度を測定します。内外反ストレステストやマクマレーテストなどの整形外科的テストを加えることで、靭帯および半月板の機能を客観的に把握します。
| 評価項目 | チェック内容 | 推察される主な疾患 |
|---|---|---|
| 視診 | 腫脹・熱感・皮下出血 | 半月板損傷、靭帯損傷、変形性膝関節症 |
| 触診 | 圧痛点・軋轢音 | 腸脛靭帯炎、鵞足炎、内外側側副靭帯損傷 |
| 可動域 | 屈曲角度・伸展角度の制限 | 変形性膝関節症、半月板損傷 |
| 徒手検査 | 内外反ストレス、回旋ストレス | 側副靭帯損傷、半月板損傷 |
画像検査: X線・超音波検査
徒手評価だけでは損傷の程度を判別しきれない場合、鶴橋整形外科クリニックではレントゲン(X線)検査を行います。体重をかけた正面像・側面像を撮影することで、関節軟骨のすり減りや骨棘形成の有無を確認し、変形性膝関節症の進行度を把握します。
超音波(エコー)検査は、腱・靭帯・滑液包など軟部組織をリアルタイムに描出でき、被ばくの心配もありません。腸脛靭帯の肥厚や半月板周囲の滑膜炎、関節液貯留を即座に確認できるため、スポーツ外傷後の早期診断に有用です。
| 検査方法 | 分かること | メリット |
|---|---|---|
| レントゲン | 骨配列、関節裂隙、骨折・骨棘 | 変形の程度を定量的に評価 |
| 超音波 | 腱・靭帯の肥厚、滑液包炎、関節液 | 動的観察が可能、被ばくなし |
自分でできる応急処置とセルフケア
RICE処置で痛みを和らげる
安静(Rest)
痛みが強い直後は患部を動かさず、イスやベッドに座る・横になるなどして膝への負担を最小限にとどめます。無理に歩き続けると炎症が拡大し、回復を遅らせる原因になります。当院では松葉杖を併用して移動距離を減らす方法も指導しています。
冷却(Ice)
受傷後48時間は氷嚢や保冷材をタオルで包み、15〜20分を目安に冷却します。冷やし過ぎによる凍傷を防ぐため、肌の感覚が鈍くなったらいったん外し、1時間ほど間隔を空けると安全です。
圧迫(Compression)
弾性包帯で軽めに圧迫することで腫れを抑え、内出血による痛みを軽減できます。ただし、締め付け過ぎは血流障害を招くため、指が1本入る程度の余裕を残すことが大切です。
挙上(Elevation)
横になる際にクッションや毛布を重ね、膝を心臓より高い位置に保つと、血液とリンパの循環が促進されます。夜間就寝時も同様に脚を少し高くすると翌朝の腫脹が軽くなる傾向があります。
| 処置 | 開始目安 | 1日の頻度 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 安静 | 痛み発生直後 | 必要に応じ随時 | 負荷をかけない姿勢を保つ |
| 冷却 | 受傷後すぐ | 15〜20分を1〜2時間ごと | 凍傷予防にタオルを使用 |
| 圧迫 | 冷却と併用 | 日中継続 | 指1本分の余裕を確保 |
| 挙上 | 安静時 | 就寝時を含む | 心臓より高く保つ |
ストレッチと筋力トレーニング
痛みが落ち着いたら関節の動きを回復させ、再発を防ぐための柔軟性向上と筋力強化を進めます。無理のない範囲で行い、痛みが増強する場合は中断してください。
ストレッチ
| 部位 | 方法 | 時間/回 | 回数/日 |
|---|---|---|---|
| 大腿四頭筋 | 立位で足首を持ち、踵を殿部に近づける | 20秒 | 2〜3回 |
| ハムストリングス | 仰向けで片脚を上げ、タオルを足底に掛けて引く | 20秒 | 2〜3回 |
| 殿部 | 椅子に座り、足首を反対側の膝に乗せて上体を前傾 | 30秒 | 2回 |
筋力トレーニング
鍛える筋群は大腿四頭筋・内転筋・中臀筋が中心です。下記は鶴橋整形外科クリニックで実際に指導している例です。
| 種目 | 姿勢と動作 | 回数 | セット |
|---|---|---|---|
| 膝伸展運動 | 椅子に座り片脚をゆっくり伸ばし3秒保持 | 10〜15 | 2 |
| 内転筋締め | 膝の間にタオルを挟み、5秒かけて押し合う | 10 | 2 |
| 横向き脚上げ | 横臥位で上側の脚を真上にゆっくり上げ下ろし | 10 | 2 |
サポーターとテーピングの活用法
当院では膝周囲の安定性を高め、日常動作の痛みを軽減させる補助具としてサポーターやテーピングを推奨しています。
サポーター
装着の目安は家事・通勤・買い物など立位や歩行が続く時間帯です。夜間は血行を妨げる恐れがあるため外してください。
テーピング
膝蓋骨の外側偏位を抑えるキネシオタイプと、内側の支持力を補うホワイトテープの併用が一般的です。貼付時間は12時間以内とし、かゆみ・発赤が出た場合はすぐに剥がしてください。
使用時のチェックポイント
- 装着後にしびれや色の変化がないか確認する
- 汗で湿ったままにせず、清潔を保つ
- 連日使用する場合は就寝前に皮膚を休ませる
以上の方法は早期回復と再発防止に有効ですが、痛みが強い・腫れが引かない・歩行困難などの症状が続く場合は、鶴橋整形外科クリニックまで早めにご相談ください。
整形外科で受ける治療法
鶴橋整形外科クリニックでは、膝を曲げたときに横が痛む患者さまの症状・原因・生活背景を総合的に評価したうえで、薬物療法とリハビリテーションを中心に治療を行っています。以下に当院で採用している代表的な方法を紹介します。
薬物療法:消炎鎮痛薬とヒアルロン酸注射
炎症を抑え痛みを軽減しながら、関節組織の回復を促すことを目的とします。年齢、基礎疾患、服用中の薬剤を確認し、副作用リスクを最小限に抑えた処方を心がけています。
| 治療法 | 主な適応 | 期待される効果 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 非ステロイド性抗炎症薬(内服) | 腸脛靭帯炎・鵞足炎・半月板損傷に伴う疼痛 | 炎症抑制、痛みの速やかな軽減 | 胃腸障害や腎機能低下がある方には慎重投与 |
| 消炎鎮痛外用薬 | 皮膚刺激が少ないケースでの局所痛 | 貼付部位の血流改善と鎮痛 | かぶれやすい体質では使用時間を短縮 |
| ヒアルロン酸関節内注射 | 変形性膝関節症・半月板損傷後の関節機能低下 | 関節軟骨の保護、滑液の粘度改善による動作時痛の緩和 | 注射後24時間は強い運動を控える |
内服薬
急性炎症が強い場合は非ステロイド性抗炎症薬を短期間集中的に使用し、その後は胃粘膜保護剤や漢方薬で調整します。高齢者や腎疾患を有する方にはアセトアミノフェン主体の処方を検討します。
外用薬
貼付型やゲル型の消炎鎮痛薬を併用し、内服量を抑えながら局所の疼痛をコントロールします。貼付位置は痛みの出るラインに沿わせ、就寝前に皮膚を休ませる時間を設けます。
関節内注射
週1回を目安に3~5回実施し、その後は状態に合わせて間隔を延ばします。当日は注射部位の清潔を保ち、腫脹が強い場合は自宅でアイシングを継続してください。
リハビリテーションで関節機能を回復
薬物療法だけでなくリハビリテーションを併用することで治癒までの期間短縮と再発防止が期待できます。当院の理学療法士がマンツーマンで対応し、痛みの程度に合わせたプログラムを組み立てます。
物理療法
超音波治療器や温熱療法で軟部組織の血行を促進し、筋緊張をやわらげます。急性期には低出力の超音波治療を、慢性期にはホットパックを併用しながら筋肉の伸張性を高めます。
運動療法
大腿四頭筋・内転筋・ハムストリングスの協調性と柔軟性を高めるエクササイズを中心に実施します。痛みが出ない範囲で膝を曲げ伸ばしし、荷重ラインが外側または内側に偏らないよう動作指導を行います。
装具療法
歩行時のぐらつきが強い患者さまには、短時間でもサポーターを活用し関節周囲への負担を一時的に軽減します。装着時間や圧迫度は理学療法士が細かく調整し、筋力低下を招かないよう段階的に離装します。
鶴橋整形外科クリニックでは、これらの治療を組み合わせることで、患者さま一人ひとりの生活スタイルに寄り添いながら膝の横痛改善を目指しています。症状が長引く場合やセルフケアで効果が乏しい場合は、お気軽にご相談ください。
生活習慣の見直しと再発予防
鶴橋整形外科クリニックでは、痛みが改善した後も生活習慣を見直して膝への負担を長期的に減らすことを再発防止の要と考えています。ここでは実際に外来指導でお伝えしている内容を中心に解説します。
体重管理で膝への負担を減らす
膝にかかる荷重は体重の約3〜5倍といわれ、わずかな体重増加でも関節軟骨や靭帯へのストレスが増大します。当院では「1か月に体重の1〜2%減」を目安に無理のない減量を勧めています。
| 現在の体格指数 | 推奨される減量幅 | 主なポイント |
|---|---|---|
| 22未満 | 維持 | 筋力維持を優先 |
| 22〜25 | 1〜2㎏ | 間食の内容を見直す |
| 25以上 | 3㎏以上 | 夕食後の炭水化物を半分に |
食事指導では、揚げ物や清涼飲料水を控える「質の改善」が効果的です。当院管理栄養士による個別カウンセリングもご活用ください。
正しい歩行と姿勢を身につける
歩幅が狭く膝が内側に入る「内股歩行」は、内側半月板や内側側副靭帯を過度に引き伸ばします。理学療法士が実施する歩行分析では、
- 踵からつま先へ重心を移すローリング動作
- 骨盤を水平に保ち膝がぶれないライン
- 上半身を少し前傾し腕を振るリズム
を確認し、個別に矯正します。また長時間の座位は30分に1回立ち上がることで血流を促進し、関節包の栄養補給を助けます。
インソールとサポーターの併用
外側荷重が強い方には外側楔状インソールを処方し、内側コンパートメントの圧を分散させます。サポーターは日中の活動時間のみ装着し、就寝時は外して関節を解放してください。
運動前後のウォームアップとクールダウン
急な方向転換やジャンプ動作は膝靭帯損傷の引き金になります。運動前後に以下のメニューを5〜10分行いましょう。
| タイミング | 主な内容 | 期待できる効果 |
|---|---|---|
| ウォームアップ | 膝回し・股関節開閉・かかと上げ | 関節液循環が高まり軟骨摩耗を防ぐ |
| クールダウン | 大腿四頭筋とハムストリングスの伸張運動 | 筋肉の張りを軽減し炎症を抑える |
運動後30分以内に太もも前面に氷水で10分冷却すると微細損傷の修復が促進され、翌日の痛みが軽減します。
週3回・各15分の筋力トレーニング
膝を支えるのは大腿四頭筋だけでなく、中殿筋や腹横筋など体幹筋群も重要です。以下の自重運動から始め、フォームが安定してから回数を増やします。
- 椅子に座ったまま膝を伸ばすレッグエクステンション 10回×3セット
- 横向きに寝て脚を持ち上げるアブダクション 15回×2セット
- 壁に背をつけたスクワット 30秒キープ×3回
痛みが強い日は休養を優先し、炎症症状(熱感・腫れ)があればアイシングと安静を徹底してください。
よくある質問
階段の上り下りで痛いときの対処法
階段では体重の3〜4倍の負荷が膝にかかるため、横(外側・内側)の痛みが強く出やすくなります。まず手すりを使い、痛む側の足を後に出すことで衝撃を軽減してください。歩幅を狭くし、つま先と膝が同じ方向を向くよう意識すると靭帯へのねじれストレスが減ります。
| 状況 | 推奨される動作 | 注意点 |
|---|---|---|
| 上り | 手すり側の足から踏み出す | 痛む足は一段ずつ後追い |
| 下り | 痛くない足から降りる | 膝を深く曲げない |
| 痛みが強いとき | エレベーター・エスカレーターを活用 | 無理に段差を使わない |
当院では超音波(エコー)検査で腱や靭帯の炎症状態を把握し、痛みの原因を特定します。階段動作が難しいほどの痛みがある場合は早めにご相談ください。
痛みが二週間続く場合の受診目安
打撲や軽い捻挫の場合、数日で落ち着くことが多いですが、二週間以上痛みが続く場合は何らかの組織損傷や慢性炎症が疑われます。特に次のサインがある場合は速やかな受診が必要です。
- 夜間痛や安静時痛が強い
- 膝の腫れ・熱感が増している
- 歩行時にガクッと崩れる感じがある
受診の際は、痛みが出た経緯・これまで行ったセルフケアをメモしてお持ちいただくと診察がスムーズです。鶴橋整形外科クリニックではレントゲンで骨配列を確認し、必要に応じてエコーで半月板や靭帯の状態を評価します。
サポーターは寝るときも着けるべきか
サポーターは日中の活動時に関節を安定させ、痛みを抑えることが主な目的です。就寝時は膝への荷重がほとんどないため、通常は外して構いません。ただし、寝返りで痛みが出る・夜間に膝が外側へ倒れやすい場合は、柔らかい薄手のサポーターやタオルをゆるく巻く方法もあります。
着用を続ける際は以下を確認してください。
- 圧迫が強すぎて血流が阻害されていないか
- 皮膚トラブル(かゆみ・発赤)が出ていないか
- 朝起きてむくみが強い場合は外して休む
サポーターの着脱タイミングに迷う場合は、診療時にお気軽にお尋ねください。患者さま一人ひとりの生活スタイルに合わせて、最適な使い方をご提案いたします。
まとめ
膝の横が曲げると痛む場合、外側では腸脛靭帯炎、内側では変形性膝関節症など原因が分かれます。整形外科で画像検査を受け正確に診断し、急性期はRICE処置、慢性期はストレッチと筋力強化で機能を回復しましょう。体重管理や正しい歩行を続けることで再発を抑えられます。二週間以上痛みが続く、階段がつらいなどの際は早めに医師へ相談が必要です。痛みが取れない、違和感があるなどお困りごとがありましたら当院へご相談ください。